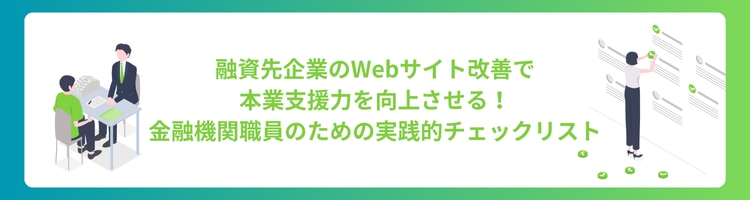
融資先企業のWebサイト改善で本業支援力を向上させる!金融機関職員のための実践的チェックリスト
融資先企業のWebサイト改善提案で、本業支援力と顧客との関係性を向上させたい金融機関職員の皆様へ。
この記事では、金利の話だけで終わらない商談を実現するための具体的なチェックリストと実践方法を解説します。顧客の経営課題を発見し、真に頼られるパートナーとなるための第一歩を、ここから始めましょう。
目次[非表示]
はじめに:あなたの商談に「新しい武器」を
「また今日も金利の話だけで終わってしまった...」
地域金融機関で働く多くの職員が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。低金利時代が続く中、従来の融資中心の営業だけでは、取引先企業との関係深化は困難になっています。
しかし、実は皆さんの目の前に、**顧客との関係性を劇的に変える「隠れた支援ポイント」**が存在します。それが、融資先企業の「Webサイト」です。
なぜWebサイト改善提案が本業支援の突破口になるのか
注目すべき市場データ:中小企業のデジタル化の現状
中小企業庁の調査によると、従業員数20名以下の小規模事業者のうち、**約60%が「自社のWebサイトに課題を感じている」**と回答している一方で、具体的な改善策が分からないと悩んでいる経営者が大半を占めています。
さらに、コロナ禍を経てオンラインでの情報収集が当たり前となった現在、BtoB取引においても約80%の企業が取引先選定時にWebサイトを参考にしているというデータがあります。
つまり、多くの中小企業が「Webサイトの重要性は理解しているが、どう改善すれば良いか分からない」状況にあり、これは金融機関職員にとって絶好の支援機会なのです。
金融機関職員がWebサイト改善支援に取り組むべき3つの理由
1. 決算書では見えない経営課題を発見できる
財務数値は過去の結果ですが、Webサイトは企業の「今の営業力」を表しています。売上低迷の原因が、実はWebサイトの問題だったというケースは少なくありません。
2. 他行との明確な差別化が図れる
多くの金融機関がまだ手薄な領域のため、先行優位性を確立できます。「あの担当者に相談すると、経営の本質的なアドバイスがもらえる」という評判につながります。
3. 継続的な接点創出が可能
Webサイト改善は一度で完結せず、継続的な改善が必要です。定期的な訪問理由ができ、長期的な支援関係を構築できます。
5分でできる!訪問前のWebサイト事前チェック手法
取引先を訪問する前に、以下のポイントで簡単にWebサイトをチェックしましょう。
基本チェック(所要時間:3分)
- スマートフォンで見やすいか:今や顧客の7割以上がスマホでアクセス
- 会社の強みが3秒で分かるか:トップページを見て何の会社か瞬時に理解できるか
- 連絡先がすぐに見つかるか:問い合わせしたい顧客が迷わないか
営業視点チェック(所要時間:2分)
- 競合他社と比較してどうか:同業他社のサイトと見比べて差別化できているか
- 更新頻度はどうか:最新情報が半年以上更新されていないのは要注意
- 顧客の声や実績が掲載されているか:信頼性を高める要素があるか
実践!融資先企業Webサイト改善チェックリスト
以下のチェックリストを活用して、取引先企業のWebサイトを体系的に診断しましょう。各項目は、商談時の具体的な提案材料になります。
【経営戦略観点】経営者の想いが伝わるサイトになっているか
□ 企業の強み・差別化ポイントが明確に表現されている
- 「技術力」「品質」「サービス」など、具体的な強みが分かりやすく説明されているか
- 提案例:「御社の○○という技術的強みが、サイト上ではもっと分かりやすく表現できそうですね」
□ ターゲット顧客に響くメッセージになっている
- BtoB企業なら企業向け、BtoC企業なら一般消費者向けの言葉遣いになっているか
- 提案例:「お客様のターゲット層を考えると、もう少し専門的な表現を使った方が良いかもしれません」
□ 事業承継後の新体制・新方針が反映されている
- 後継者が就任している場合、新しいビジョンや取り組みが紹介されているか
- 提案例:「新社長の想いやビジョンをサイトで発信することで、既存顧客の信頼獲得にもつながりますよ」
【営業・マーケティング観点】売上につながる仕組みがあるか
□ 問い合わせ導線が分かりやすく設計されている
- 電話番号やメールアドレスが見つけやすい場所に配置されているか
- 提案例:「問い合わせボタンをもっと目立たせることで、商談機会を逃さずに済みそうですね」
□ 既存顧客の声・実績が効果的に掲載されている
- お客様の声、導入事例、受賞歴などが信頼性の向上に役立っているか
- 提案例:「○○様からいただいた感謝のお声を掲載すれば、新規顧客の安心感につながります」
□ 競合他社との差別化が明確に表現されている
- 同業他社と比較して、選ばれる理由が明確になっているか
- 提案例:「競合A社と比べて、御社の○○という特徴をもっと前面に出せそうですね」
【運用・組織観点】継続的な改善体制が整っているか
□ 更新体制・責任者が明確になっている
- 誰がサイトの更新を担当し、どのくらいの頻度で見直しているか
- 提案例:「後継者育成の一環として、若手社員にWeb担当を任せてみるのはいかがでしょうか」
□ 後継者育成の観点でデジタルスキルが蓄積されている
- 次世代の経営陣がデジタルマーケティングに理解を示しているか
- 提案例:「デジタルネイティブ世代の社員を巻き込むことで、組織全体のIT化が進みそうですね」
□ コスト対効果が適切に管理されている
- サイト運用にかかる費用と、得られる効果のバランスが取れているか
- 提案例:「月々○万円の投資で、年間○件の問い合わせ増加が期待できれば、十分な投資効果がありますね」
顧客への提案方法と実践的コミュニケーション術
「上から目線」にならない提案アプローチ
❌ 避けるべき表現 「御社のホームページは古くて使い物になりません」 「これでは顧客が来るわけがないです」
⭕ 推奨する表現 「御社の技術力を考えると、もっと多くの方に知ってもらえる余地がありそうですね」 「サイトを少し工夫するだけで、問い合わせが増える可能性を感じます」
経営者が納得する「数字で語る」改善効果の伝え方
業界平均データを活用した説得力のある提案
- 「製造業の場合、Webサイトからの問い合わせが売上の約15%を占めているという調査データがあります」
- 「同規模の企業様では、月間サイト訪問者数が○○件程度が一般的です」
- 「BtoB企業の約8割が、新規取引先を検討する際にWebサイトを参考にしています」
段階的な提案ステップ
第1段階:現状把握と課題整理 「まずは現在のサイトの状況を整理してみましょう」
第2段階:改善可能性の提示
「こちらの3つのポイントを改善すれば、効果が期待できそうです」
第3段階:具体的なアクション提案 「信頼できる専門パートナーをご紹介できますので、一度相談してみませんか」
まとめ:本業支援のプロフェッショナルとしての成長
Webサイト改善支援から始まる総合的な経営改善支援体制
融資先企業のWebサイト改善支援は、単なる「IT支援」ではありません。これは、顧客企業の経営課題を発見し、継続的な改善を支援するという、まさに金融機関に求められる本業支援そのものです。
決算書の数字だけでは見えない「営業力」「ブランド力」「組織力」といった経営資源の課題を発見し、具体的な解決策を提案できる金融機関職員こそが、これからの時代に顧客から真に頼られる存在になります。
地域金融機関としての新たな価値提供の可能性
デジタル化が進む現代において、地域の中小企業が最も必要としているのは「身近で信頼できる相談相手」です。長年の取引関係で培った信頼関係をベースに、最新のデジタルマーケティング支援を提供できる金融機関は、地域経済の発展に欠かせない存在となるでしょう。




