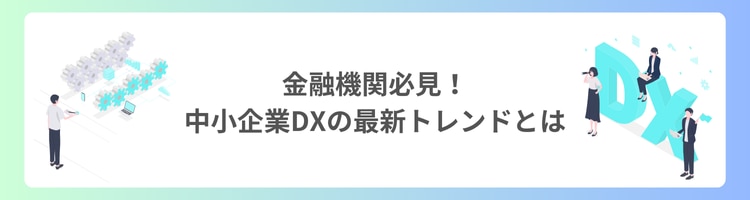
金融機関必見!中小企業DXの最新トレンドとは
事業承継や人材不足、競争激化…中小企業を取り巻く経営環境は、ますます厳しさを増しています。
一方で、近年DX(デジタルトランスフォーメーション)が“選択肢”ではなく“必要条件”になりつつあります。
金融機関は、単なる資金供給者にとどまらず、中小企業のDXを支援する「本業パートナー」としての期待も高まってきています。
本記事では、中小企業DX支援を意識する金融機関担当者が押さえておくべき最新トレンド5つを整理し、
それぞれについて現場視点・導入時の留意点を交えて解説します。
これらを理解することで、融資先との関係強化や新たなビジネス機会の創出につなげられるでしょう。
目次[非表示]
はじめに — なぜ今、DX支援が金融機関の“主戦場”なのか
銀行・信用金庫といった金融機関が中小企業DX支援を志向する理由は大きく3つあります。
1.差別化と競争力向上
従来の利ザヤ型ビジネスはレッドオーシャン化する中、DX支援を武器に他行との差異化を図る必要があります。
2.リスク低減と債権品質向上
DXを通じて、企業の業務・収益の見える化が進めば、債務者の経営状態をリアルタイムに把握でき、危機兆候を早期発見できます。
3.新たな収益モデル創出
Embedded Finance や API を起点に、金融サービスを“業務プラットフォーム”に埋め込むビジネスモデル構築が可能になります。
しかし、闇雲にDX支援を打ち出せば、導入定着化に至らず顧客に見切られるリスクもあります。
だからこそ、最新トレンドを正しく捉え、現場実装可能な支援モデルを構築することが重要です。
埋め込み型金融(Embedded Finance)の実運用化
概要と意義
Embedded Finance (埋め込み型金融)は、SaaS や業務プラットフォームの中に決済、貸付、ファクタリング、保険といった金融機能を“埋め込む”方式です。中小企業にとっては、業務アプリケーションを利用する延長線上で資金調達や与信機能を手軽に利用できる“自然な流れ”が生まれます。
金融機関視点の注目点
顧客接点強化:業務アプリケーションに“金融の入口”を設けることで、従来の支店窓口・営業チャネルを越えた接点を獲得できます。
利用率・取引額拡大:埋め込まれた金融サービスは、小口・短期の利用がされやすく、取引量拡大の可能性があります。
リスク管理の新局面:与信モデルや債権管理プロセスを「API時代/リアルタイム対応型」に刷新する必要があります。
現場での検討・導入課題
パートナー選定:プラットフォーマー側の信頼性や契約条件、API品質などを精査する必要があります。
UX設計:ユーザー動線を阻害しないシームレスな設計が不可欠。画面遷移、認証方法、エラー時レスポンスなど細部設計が鍵を握ります。
手数料・収益モデル:手数料収益や分配スキームの設計をどうするか(プラットフォーマーとの取り分・コスト分担)を明確に。
実践ヒント(営業現場向け)
埋め込み型金融の導入を狙う際には、まずは既存のSaaS連携先(会計、販売管理、請求管理等)を起点に、小規模な実証実験を行うのが有効です。成功事例を作り、利用実績とリスクを蓄積しながら拡張していくやり方が現実的です。
地域・中堅金融機関のBaaS(Banking as a Service)/
APIファースト戦略
概要と潮流
BaaSとは、銀行がAPIを公開して、自社の金融機能を他社(プラットフォーム事業者、ITベンダーなど)にサービスとして組み込ませる形態です。特に地方銀行や信用金庫では、地域の基幹業務プラットフォーマーと連携して地域DXを牽引する期待が高まっています。
金融機関にとっての強み
自行資源活用:もともと持っている決済・与信・口座機能を外部基盤として展開でき、投資効率を最大化できます。
関係深化:地域事業者・プラットフォーマーとの接点が増えることで、商流(流通チャネル)へのアクセス機会が広がります。
中小企業囲い込み:業務プラットフォームと金融を一体で提供できれば、他行への乗り換えコストを高められます。
実務的なポイントと注意事項
API設計の品質:信頼性・可用性・セキュリティを担保したAPI設計が不可欠であり、SLA(Service Level Agreement)体制が必要です。
ガバナンス体制の構築:API提供に伴うリスク(不正アクセス、責任所在等)を整理し、契約・責任分界点を明確にしておく必要があります。
災害対応・冗長構成:システム障害や負荷集中時の対応設計、冗長化・バックアップ戦略を整備しておくことが不可欠です。
先行活用例
地域密着型クラウド基盤や地域業者向け業務SaaSと手を組み、地域DXパッケージを提供する事例があります。
こうしたケースは、地方銀行が“地域DXのハブ”として振る舞うモデルです。
基礎DX整備の遅れがもたらすギャップと対策
問題提起
多くの中小企業では、AIや高度分析に飛びつく前に、会計クラウド、請求書のデジタル化、ドキュメント管理、基幹システムの電子化といった“基礎DX” が未整備である状態が散見されます。高度DXツールを入れても、土台がぐらついていたら効果は限定的です。
金融機関の支援対象として重視する領域
会計クラウド/クラウド会計ソフトの導入支援
電子請求・e-インボイス連携
文書管理・ワークフローのデジタル化
データ基盤強化(CSV/APIで他システムと連携できるようにする)
社内IT基盤(ネットワーク、クラウド環境、バックアップ、セキュリティ)整備
支援実行での留意点
“目的から逆算”型支援:最初に業務課題をヒアリングし、「このギャップがDX導入を妨げている」領域を洗い出す
導入の簡易性重視:複雑なものや過剰機能なものを最初から導入せず、スモールスタートで成果を出す
定着化・伴走支援:現場の定着プロセスを設計し、継続フォローを組み込む(操作支援・改善提案)
金融機関としての提案切り口
「まずはこの3つを一緒に整えましょう」という標準DXスターターパッケージ(会計+請求+文書管理)を設計し、補助金申請支援とセットで提供できる体制を用意しておくと提案しやすくなります。
代替スコアリングとリアルタイム与信モデルの進化
背景と市場期待
従来の与信モデルは、決算書・試算表を基にすることが中心でした。しかしそれでは売上・支出変動の激しい企業、成長初期段階企業などを的確に評価できないという課題が残ります。そこで注目されているのが、電⼦請求データ、POS・EC売上、購買履歴、入出金フローなどの“代替データ”を活用したスコアリングモデルです。
金融機関にとっての可能性
与信スコアリング精度向上:従来モデルが苦手とする業態・ステージへの対応が可能になる
審査速度改善:リアルタイムデータ活用により迅速審査を実現
リスクモニタリング向上:変動性の高い経営環境下でも早期警戒サインを発見できる
実装の検討ポイント
データ収集インテグレーション:プラットフォーム・SaaSとのAPI連携を構築し、データ取得基盤を整備する
モデル開発・検証:機械学習モデルや統計モデルの設計・精緻化と、貸倒・デフォルト実績との検証
説明責任と透明性:モデルブラックボックス化を避け、スコア算出ロジック(ある程度)説明可能な仕組みを整える
倫理・法令遵守:個人情報・顧客データの取り扱いに関する規制をクリアし、適切な同意取得と匿名化設計も必要
導入ステップ案
一部取引先(特定業種)で代替データを用いたスコアリングを並行運用
モデルの予測精度・債務不履行率をモニタリング
成果が確認できれば、既存与信モデルへの導入展開
規制政策とサステナビリティ志向の高まり
政策・制度の後押し
日本政府・関係機関は、中小企業の生産性向上やデジタル化支援を政策の柱の一つと位置づけています。金融庁・関係省庁は、DX支援を行う金融機関に対して評価を与える方向性を出しており、金融機関には“社会的責任”や“地域貢献”という文脈でDX支援が期待されています。
ESG・サステナビリティとの融合
DXを通じて省エネ・紙レス化・効率化を実現できれば、環境面(E)の側面で評価できる余地があります。また、ガバナンス強化や労働生産性向上という文脈で、金融機関自身のSDGs投資・融資判断におけるスコアリング要件にも反映されつつあります。
実務対応上のポイント
補助金・助成金の活用:国・地方自治体が実施するDX支援助成制度を把握し、組み込み提案できる体制を整える
CSR/ESG報告のバリュー訴求:DX支援先企業の成果を事例化し、自行のSDGs施策や地域貢献姿勢を発信
リスク対応視点:デジタル化が進むほど、サイバーリスク・データ流出リスクも高まる。セキュリティ支援体制をセットで提供できるようにしておく
まとめ:5大トレンドを自行DX支援設計に落とし込むために
本稿でご紹介した最新5つのトレンドを振り返ると、それぞれが中小企業DX支援における“新たな接点”と言えます。
Embedded Finance:業務体験と金融体験の融合
BaaS / API ファースト戦略:金融機能のオープン化・展開
基礎DX整備の遅れ是正:DXの土台を固める支援優先
代替スコアリング/リアルタイム与信:高度与信モデルの革新
政策支援 & ESG一体化:制度後押しと社会志向評価
金融機関がこれらを自らの「支援ポートフォリオ」に落とし込み、「どこから着手すべきか」の選択肢を持つことが重要です。
以下は、導入を検討する際の優先判断軸/チェックリストです。
優先判断軸(導入検討時のガイドライン)
判断軸 | 主な観点 |
|---|---|
顧客ポートフォリオ適合性 | 取引先の業種・業態・ITリテラシー水準との親和性を見極める |
投資対効果 | 初期開発/運用コストに見合う収益性・リスク低減効果が見込めるか |
拡張性・スケール性 | 実証後に全国展開・他SaaS連携に耐える構造か |
ガバナンス・リスク対応 | セキュリティ設計、責任分界点、法令コンプライアンス整備体制 |
定着/運用サポート体制 | 顧客現場へ定着させる人的体制や改善ループをどう設計するか |
取り組み優先順の一例(モデルケース)
自行顧客・既契約SaaSとの連携可能性を調査
基礎DX支援パッケージ(会計 + 請求 + 文書管理)を企画
一部取引先で代替データスコアリングを試行
埋め込み型金融 / BaaS連携検証を併行
成果が確立できた領域から横展開・スケール化
おわりに — “提案者”から“共創者”へ
DX支援を通じ、金融機関は顧客中小企業の“提案者”から、事業変革を共に歩む“共創者”へと役割を変えていく時代に差し掛かっています。
単なる資金供給者ではない“成長のパートナー”として、企業が必要とするDX基盤や金融機能を提供できれば、
顧客ロイヤルティと新たなビジネス価値を同時につかめます。
本稿の5大トレンドを踏まえ、まずは小規模な実証実験から着手することを推奨します。
現場課題を丁寧に拾いながら成功モデルを形成し、それを拡張していくことが重要です。
金融機関の皆様が、中小企業の変革を支える先導者として、未来を切り拓かれることを心より願っております。
宣研ロジエ株式会社では取引先の広告運用支援など、金融機関のパートナーとしてお手伝いいたします。
中小企業だからこそできる、お取引先様と目線を合わせたきめ細やかで、現実的な支援をご提供いたします。
地方銀行や信用金庫の実績もございますので、是非お気軽にお問い合わせください。




